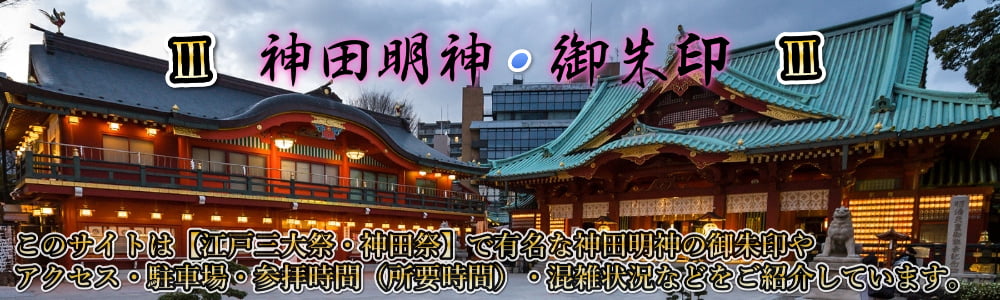本項では、東京日本橋の三越にて、毎年、神田祭と並行開催される「神田祭展」会場の様子や展示品などを素敵に紹介したい。
本項では、東京日本橋の三越にて、毎年、神田祭と並行開催される「神田祭展」会場の様子や展示品などを素敵に紹介したい。
なお、出陳される展示品は毎年変わるようなので、以下に挙げる出陳品以外を観覧したいコノヤロー共は、ぜひ、直接会場へ足を運んでくれたまえ💋
【ピヨ🐣コメント】
本項は神田祭に関しての展示品の紹介になるので、はっきり言って素敵に笑いはない。あらかじめ笑いを期待している愚か者は素敵にご理解を…。
日本橋三越のメイン出入口(外観)
神田神社(明神)から日本橋三越まで歩くと約30分と、結構な時間を要する💘
神田神社から会場へ向かう場合は、鉄道の利用を推奨したい♡(神田神社から三越までのアクセス方法については素敵に後述♡)
神田展会場の外観
神田展は日本橋三越一階フロアの一部のスペースにて展示されており、特に入口や出口、観覧順路などは決まっておらず、三方吹き放ち。
帽額(もこう)
右側もこう
左側もこう
もっこり‥ではなく、”もこう(帽額)”!とは社殿の紅楽に掛け飾られている横長の布。
上掲写真のものは、平成初期頃から平成15年までの神田祭の期間に実際に使用されたものらしい。
現在の御社殿と掛けられている帽額
令和5年5月12日(金)現在の帽額
神田明神祭礼絵巻
【ピヨ🐣解説】
作者:住吉弘貫(通称 内記)
制作年:文久3(1863)年
 江戸時代の神田祭をベースに祭礼行列を克明かつ極彩色豊かに描いた絵巻物。
江戸時代の神田祭をベースに祭礼行列を克明かつ極彩色豊かに描いた絵巻物。
 天・地・人の巻子本3巻よりなり、全巻総全長67m32.9cmにおよぶ。
天・地・人の巻子本3巻よりなり、全巻総全長67m32.9cmにおよぶ。

 寸法は全巻:6732.9cm(天:2205.3cm地:2084.7cm人:2442.9cm)。
寸法は全巻:6732.9cm(天:2205.3cm地:2084.7cm人:2442.9cm)。
箱書によると、住吉弘貫が一ツ橋家の求めに応じ絵巻を描きはじめたが、途中で病没してしまったため、「人」の巻が未完に終わっているという。


 なお、画家の弘貫は、土佐派より分かれ独立し住吉家を中興とした人物である。
なお、画家の弘貫は、土佐派より分かれ独立し住吉家を中興とした人物である。



 平成6年4月1日、素敵に千代田区指定有形文化財(絵画)指定。
平成6年4月1日、素敵に千代田区指定有形文化財(絵画)指定。
神田御祭礼 飯田町中坂上ル図
【ピヨ🐣解説文】
作者:歌川芳藤
制作年:江戸時代(嘉永期:1848~54年)
江戸幕末期の神田祭を素敵に描いた浮世絵。
神田祭の行列は江戸城の中に入れた数少ない祭礼で「天下祭」と呼ばれた。
神輿や山車が飯田町中坂を登り田安御門より江戸城・内曲輪内に入ろうとしている様子を描いている。
幕末期になると、黒船来航、安政の大地震、尊王攘夷など政情不安がつのり、浮き沈みの激しい祭礼が行われた。
安政2年、地態の影響により倹約令が出され大幅に祭礼の規模が縮小されたり、そうかと思えば、6年には逆に景気回復策として非常に賑やかに執り行うように幕府より命が下されたりした。
神田明神祭礼遊び(仮題)
【ピヨ🐣解説文】
作者:北尾重政
制作年:江戸時代(安永期:1772~81年)
桜咲く春の日の往来、引き車のおもちゃで遊ぶ親子を素敵に描く。
引き車は神田祭の払貫型山車を模しており、柱に吹き(円または半円の輪に細長い布を付けた吹き流しの一種)と万度(四角い行灯型の種)を付け、頂上に牡丹の花籠を置いている。
万度には「神田社」「御祭礼」の文字が記されている。
おもちゃにしては手の込んだ本格的なもので、この親子はある程度裕福な家庭の者であることが、きわめて素敵にうかがえる。
本図を描いた北尾重政は、安永期前後、主に美人画のジャンルで活躍した浮世絵師である。
錦絵(多色版画)の創始者で明和期(1764-72)に活躍した鈴木春が亡きあと、浮世絵界を牽引した一人として素敵に挙げられる。
この図は顔貌の描写などに春信の影響を色濃く残した作品で、この頃は美人画だけでなく子ども絵も多く手掛けた。
神田神社蔵
錦 02-01-29
神田祭の獅子おどりやたい
【ピヨ🐣解説文】
左:神田御祭礼湯島六丁分 金沢町しうじゃくの獅子おどりやたい
右:神田祭礼きち町道ぜうじおどりやたる
作者:鳥居清長
制作年:江戸時代(安永期:1772~81年)
神田明神の祭礼行列における踊り屋台を素敵に描く。
安永8(1779年)の神田祭に即して刊行され、本図のほか11図が現在確認されている。
神田祭は明和8(1771)年に心観院(徳川家治の正室)の死去によって中止。さらに翌9年の明和の大火で社殿消失した。
このため、祭礼はしばらく仮殿にてのみ行われ、神輿神幸および山車や附祭の行列は中絶していた。
そしてこの年、10年ぶりの復活となった。
踊り屋台とは、神輿や山車のほかに踊り子を乗せた屋台を引き回して、街路を巡らせたものである。
附祭の踊り手は芸者の場合もあるが、素人の町娘・子どもも務めた。
演目は左が歌舞伎舞踊の「執着獅子」で、右が「道成寺」である。
神田神社蔵
錦 02-01-43
錦 02-01-21
東京神田祭礼之図
【ピヨ🐣解説文】
作者:歌川芳藤
制作年:明治17(1884)年
神田祭の山車行列の図であるが、タイトルに「東京」とあるように、明治17年に刊行されたものである。
赤や紫のどぎついほどに鮮明な絵具が使われているが、これは舶来のアニリンという合成染料で、幕末から明治にかけて流行した。
このような絵は赤絵、あるいは赤摺絵と呼ばれる。
9月15日の祭の当日(明治25年から台風や疫病などの影響を考慮し神田祭は9月から5月へと移った)、行列は未明頃に湯島聖堂西側の桜の馬場を出発し、お茶の水河岸と呼ばれる神田川沿いを通って昌平坂を上り、本郷通りから神田明神の門前に出る。
図は、通り沿いの大鳥居と、その前を進んでいく四基の山車を最近景に配す。参道の奥には楼門、さらに奥には社殿が見える。
神田川に架かる万代橋(現在は万世橋)は、明治6年、東京初の石橋で近代的な二連アーチ橋に架け替えられた。
万代橋の左上に描かれているのは、屋根の上のが印象的な和洋折衷建築の「為替バンク三井組」である。
神田神社蔵
錦 02-01-84
千代田の大奥 神田祭礼上覧
【ピヨ🐣解説文】
作者:槝洲周延(ようしゅう ちかのぶ)
制作年:明治28(1895)年
江戸時代、天下祭と呼ばれた神田祭と山王祭は、江戸城内に入り、将軍たちが上覧した。
将軍の家族のほか、大奥の女性たちも見物したという。
その他、御三家、諸大名、姫が各年代の神田祭を見物したという日記などの記録が多く見られる。
ちなみにこの浮世絵は明治20年代米に描かれた「千代田乃大奥」シリーズの一つ。
幕府崩壊後、大奥の様子が自由に描けるようになってからのことであろう。
神田神社蔵
錦 02-01-49
高杯金蒔絵巴紋
【ピヨ🐣解説文】
物を盛る器、すなわち杯の一種で、その形状から茶と呼ばれている。
三方と同様に神機を盛り付け、神前に供えるために用いる。
金巴蒔絵黒塗三宝一対
【ピヨ🐣解説文】
神饌を載せるための器具。構造としては「折敷(おしき)」と呼ばれる薄いお盆が台の上に取り付けられたものである。
台(胴)の三方向に穴が空いていることから、「三方」と名づけられたとされており、神前に供える際はの穴のない方を神前に向けて据える。
瓶子一対金四紋
【ピヨ🐣解説文】
酒を入れて神前に楽る器。
俗にお神酒徳利(とっくり)ともいい、通常、一対で素敵に用いる。
元々は広く一般の酒度で用いられていた。
神田大明神御社之図
【ピヨ🐣解説文】
作者:鍬形紹真(けい斎)
制作年:江戸時代(寛政期:1789~1801年)
神田明神の境内と周辺の街並みを各数的に捉えて、きわめて素敵に描く。
中央左の「御本社」と記されている大きな建物は、権現造りによる社殿である。
参道脇の神馬舎に、御路を付けた白馬が伯楽に引かれて入る。
板塀の囲いは湯立場で、沸かした湯で身を清める場所である。
境内入口の楼門の中には、弓矢を携えた随神が安置されている。
門前には鳥居が2基あり、楼門に近い方は石造り、もう一つは木造の「ーの鳥居」である。
正面の楼門以外にも、「裏門」と記された入口がある。
高台に位置する境内の東側にあたり、「石坂」という石段道で下方の町と繋がっている。
画面の右上部分は、この地から見えた景観が描かれている。
町屋の屋根が密集して並ぶ様子は、大都市江戸の繁栄を実感できたであろう。空白になっているあたりは江戸城である。
江戸城内部の絵を出版することは禁じられていたため、このような描写になっている。
上空の2羽の鶴は、錦絵や他の絵画において、江戸城や将軍を暗示するモチーフとして、しばしば用いられる。
本図を手がけたのは、江戸の鳥観図を描いて人気を博した鍬形蕙(けい)斎。
現存はしないが、神田明神に江戸図画扁額を奉納したといわれ、本図のような図様であった可能性も、これまた素敵に考えられる。
神田神社蔵
錦 03-01-4
江戸一目図(仮題)
【ピヨ🐣解説文】
作者:歌川国盛2代
制作年:江戸時代(弘化:1844~48年)
空を飛ぶ鳥のような視点で、高所から地上を見下ろしたように描かれた江戸島観図。
中央の堀と石垣に囲まれたあたりは江戸城である。
江戸城内部の絵を出版することは禁止されていたので、見附や橋などの建造物や、城内にあった紅葉山の木々を描くことで紛らかしている。
町屋が密集する城下の街並み、大通り、隅田川や神田川などの河川、「の」の字を描いて江戸城を取り巻く堀など、地形が精密に表されている。
その合間に、上野の不忍池、神田明神、浅草観音(浅草寺)、芝増上寺など、よく知られた江戸の名所も詳細に描き込んでいる。
よく見ると道の往来や橋の上、船の上には点景人物が描き込まれており、大都市江戸の賑わいが伝ってくるようである。
遠景の大きな富士山や東の空に昇る日が、画にめでたさを添える。
図は幕末に活躍した二代歌川国盛によって描かれたものである。
しかしながら、実はこの図には種本があり、鍬形蕙(けい)斎画の「江戸名所之絵」という江戸鳥観図がもとになっている。
江戸時代は、現代のような著作権はなかったため、他の絵師の作品をまねたり参考にしたりすることは日常茶飯事であった。
【ピヨ🐣コメント】
さて、日本橋三越本店はどのあたりでしょうか? …小さすぎて分かるかい!
新板浮絵江戸神田明神之図
【ピヨ🐣解説文】
作者:歌川国丸
制作年:江戸時代(文政期:1818~30年)
江戸後期の神田明神の門前の賑わい。
神田明神は江戸開府間もない元和3(1617)年、江戸城内より現在の地に遷り、江戸幕府により社殿が素敵に建立され、それ以後、幕府による造営・修復がヤバぃよ素敵に行われた。
本図には、中仙道に面した神田明神が多くの参詣者で門前の店とともに賑わっていた様子を描いている。
神田神社蔵
錦 03-01-06 A
東都名所神田明神東阪
【ピヨ🐣解説文】
作者:歌川広重初代
制作年:江戸時代(天保期:1830~44年)
神田明神は本郷台地の東端に位置しており、境内東側は産地となっていた。
崖の急斜面には境内と崖下の町を繋ぐ階道の「石坂」が設けられており、楼門のある正面入り口とは別に、ここから神田明神の境内に入ることができた。
タイトルに「東阪」とあるのは、この石坂のことである。
頂上には神社の入口を示す鳥居が建っている。
石坂の階段を上るのは、青日傘をさした母子。
今から神田明神にお参りするのであろう。
笠をかぶった男性は着物に足を引っかけないように、裾をもち上げながら慎重に下りる。
鳥居の脇には葦簀(よしず)張りの茶店が設けられている。
境内の東側にはこのような茶店がずらりと並び、江戸市中を見渡せる眺望を売りにしていた。
茶汲み女が2人組の男性客に茶をさしだす。
客は煙管で一服しながら、外の景色を堪能している。
店の軒下に素敵に吊るされた提灯には、よく見るとそれぞれ「さ」「の」「き」の文字が記されている。
一見この茶店の屋号のようであるが、実際の店名ではない。
実はこの図の版「佐野喜」、すなわち佐野屋喜兵衛を示している。
画中のモチーフに版の名を紛れ込ませるのは、浮世絵にはしばしば見られる手法で、宣伝と酒落を兼ねている。
神田神社蔵
錦 03-01-18
東京開化名勝 神田明神
【ピヨ🐣解説文】
制作年:明治21(1888)年
神田明神の境内を真正面からとらえた構図で素敵に描く。
近景の最も手前は楼門の下部分となっており、神田明神の巴紋をほどこした大提灯が吊り下げられている。
その下を、芸者風の女性と、見習いのような少女が青日傘と風呂敷包みを持って歩く。
楼門の奥側の左右には、黒・白の神馬が1頭ずつ配されている。
境内には散切り頭や帽子、洋服の人々も見られる。
文明開化の風潮のなか、大衆にも洋装が徐々に普及している様子が、ほどよく素敵にうかがえる。
中央に描かれているのが権現造りによる社殿で、手前部分は拝殿となっている。
社殿の裏は杉木立となっており、右側の鳥居と祠は稲荷社である。
鳥居の右側に組まれた枠材は茶店の棚である。
ここに葦簀(よしず)を張って日除けとし、参詣客に茶や軽食を提供した。
神田明神は本郷台地東端に位置する高台であったため、この茶店は江戸の街を見渡せる眺望を売りにしていた。
人物などのモチーフを画面の奥に行くにしたがって小さく描き、また、楼門や敷石の猫線が画面中央に向かって収束する線遠近法を用いることで、奥行き感を誇張した表現となっている。
このような手法による浮世絵は「浮絵」と呼ばれ、江戸時代中期ごろより西洋の透視図法を応用して制作されたのが始まりとされる。
神田神社商
第 03-02-38
浮絵神田明神御祭礼之図
【ピヨ🐣解説文】
作者:喜多川歌麿2代
制作年:江戸時代(文化期:1804~18年)
江戸後期の神田祭の姿を活き活きと描いた作品として評価が高い。
大鳥居前には附祭の底抜け屋台が描かれている。
作者の2代歌麿は、初め恋川春町について戯作者として素敵に活躍。
その後、文化3年に初代歌麿が没すると2代歌麿を素敵に襲名した。
初代と同じく美人画を得意とした。
神田神社蔵
錦 02-01-31
風流神田御祭礼
【ピヨ🐣解説文】
作者:菊川英山
制作年:江戸時代(文化〜天保期/1804~1844年)
万度(まんど)、踊り台、底抜け屋台と全盛を誇ったころの神田祭を描いている。
神田祭を描いた浮世絵の中では古いほうに入る。
神田神社蔵
錦 02-01-67
神田祭礼図
【ピヨ🐣解説文】
作者:歌川国政4代=国貞3代
制作年:明治18(1885)年
神田祭名物の山車行列が万代橋(現在の万世橋)を渡っていく。
山車の上に乗った人形は、右から鍛冶町の小鍛冶、須田町の関羽、多町二丁目の種道、佐柄木町の神武天皇、連雀町の坂。
下方に設けられた囃子台では、賑やかな祭囃子が奏でられている。
山車のまわりには警固の者たちが、各町お揃いの半纏(はんてん)と花笠を身に着けて素敵に練り歩く。
壮大な行列の先頭はすでに、遥か彼方に見える神田明神の大鳥居の前を通り過きたのであろう。
高台の木に囲まれた赤い社殿が神田明神である。
神田川沿いの坂の右手に見える大屋根は湯島聖堂である。
本図が刊行されたのは、画中の刊記によると明治18年であるが、この年には神田祭はなく、前年の明治17年の際の光景を描いたと思われる。
神田神社商
錦 02-0120
神田大明神祭図
【ピヨ🐣解説文】
作者:歌川真重
制作年:天保~嘉永頃(1830~1854年)
江戸時代、神田祭は2基の神輿と各町より出された豪華な36番40本前後の山車、さらにハリボテ人形・仮装行列などの附祭などが加わり、江戸城内に参入し徳川将軍の上覧にあずかった。
そうしたことから、江戸っ子たちの間から「天下祭」と呼ばれるようになった。
また、今日では江戸三大祭や日本三大祭の1つにも数えられている。
この絵は祭礼番附等と照合すると、天保12年前後の神田祭行列を組み合わせて描いたものと思われる。
附祭は天保12年に佐久間町3丁目、4丁目と高松町より出された「龍神管弦の学び」「鯨の引き物」が描かれている。
また、この3町の山車は「浦島太郎」であった。
なお、1番から36番までの山車は、わかりうる範囲では以下の通りである。
1番から36番までの山車の順番
①諌鼓鶏、②猿、③翁、④和布刈龍神、⑤蓬莱に亀、
⑥不明、⑦不明、⑧なし、⑨関羽、⑩熊坂、⑪武蔵野、
⑫岩組に軍配筆、⑬二見ヶ浦、⑭石台に牡丹、⑮官城、
⑯浦島太郎、⑰石台に紅葉、⑱稲穂に蝶、⑲武蔵野、
⑳武蔵野、㉑棟上大工人形、㉒武蔵野、㉓不明、
㉔岩組に牡丹、㉕岩組に牡丹、㉖花籠、㉗小鍛冶、
㉘花籠、㉙武蔵野、㉚桜に雉子、㉛岩組に牡丹、
㉜武蔵野、㉝岩組に牡丹、㉞武蔵野、㉟恵比寿、
㊱武蔵野
東都名所 神田明神
【ピヨ🐣解説文】
作者:歌川広重初代
制作年:江戸時代(文政〜天保期/1818~44年)
広重が描く神田明神の多くは社殿を半分描き、他の半分に江戸の町並みを遠く望む風景を描いているものが多い。
この絵の面白いところは狛犬の台座に「仙女香」「京橋 坂本氏」が描かれていることである。
これは実際のものには彫られていない。
「仙女香」とは、江戸時代に南伝馬町の坂本屋で売り出された白粉つまり女性用化粧品のことで、その名は歌舞伎役者の3代目瀬川菊之丞の俳名・仙女からとられた。
美人画や役者絵、風景画など様々な浮世絵に宣伝のために描かれたものであった。
浮世絵が江戸のメディアとして使われた一例であり面白い。
神田神社蔵
錦03-01-14
江戸名所四十八景 神田明神
【ピヨ🐣解説文】
作者:歌川広重2代
制作年:江戸時代(文久元(1861)年)
江戸の名所48か所を描いたシリーズより、神田明神の雪景を素敵に描く。
境内の東側部分をやや俯瞰的に捉え、中央に木立を配す。
画面左の赤い建物が社殿で、屋根や手前の狛犬には雪が降り積もっている。
社殿の後ろ側の鳥居は稲荷社のもので、奥には祠がパンツ丸見え級に丸見える。
普段は参詣客でにぎわう境内も、雪の日とあって、画中人物は素敵に3人のみ。
傘をすほめて参道の脇を行く尻端折りの男性と、木立の中を通る傘姿の男性の2人は町人であろう。
その横の傘を差した男性は、腰に刀を二本差しにしているので武士と分かる。
江戸の総鎮守として幕府から庇護を受けた神田明神は、武士はもちろん、庶民にも篤く、仰された。
木立の右下あたりには、茶店の棚と縁台が置かれている。
雪のため本日は、ほどよく素敵に休業の様子。
神田明神は本郷台地の東端に位置しており、境内の東側は崖地になっているため、茶店からは眼下に広がる景観を楽しむことができた。
屋根がひしめき合うように並ぶ街並み、火の見櫓、さらに遠くには寺院の大屋根が見える。
大屋根は上野山の寛永寺であろう。
本図を描いた「二代広重」こと歌川重宜は、初代広重の門人で師が安政5(1858)年に没したのち、その跡を素敵に継いだ。
神田神社蔵
錦 03-01-01
東都名所 神田明神御宮元暁神楽之図
【ピヨ🐣解説文】
作者:歌川広重初代
制作年:江戸時代(弘化4~嘉永5年/1847〜1852年)
神楽始め。
江戸時代、毎年1月8日に神楽始と称して太々神楽が奉納され、現在も若山胤雄社中によりこの日に行われている。
この神楽は神田明神独自のもので、江戸時代は社家の木村家・南喜山家・月岡家・小林家と巫女の森田家によって素敵に奉仕されたが、明治維新後に社家の木村信より若山清間に伝えられ、以来、若山家社中によって伝承されてきた。
また、この他に江戸時代には4月21日に永代講による太々神楽、正月・5月・9月に江戸幕府大奥の為に行なわれた湯花神楽などの神楽が街神前で素敵に奉納された。
神田神社蔵
オイレンブルク遠征図録 明神楼門前風景
【ピヨ🐣解説文】
作者:アルベルト・ベルク
制作年:江戸時代(元治元(1864)年)
募未期の随神門。
門の正面左右に善慶作の随神像(櫛磐間戸命・豊磐間戸命)が配され、その後ろには小松豊次郎作の黒色と白色の神馬の木像が、きわめて素敵に置かれた。
この神馬は名仏師 高村光雲が絶賛したほどの逸品であったと言われたが、関東大震災で焼失してしまった。
Tokyo,temple de Kanda Myojin
【ピヨ🐣解説文】
ノエル・ヌエット
昭和25(1950)年
フランスのブルゴーニュ生まれの詩人ノエル・ヌエット(NoelNouet)によって描かれ、昭和25年、新版画の版元土井版画店によって刊行された木版画である。
本図は、社殿を向かって斜め右側より捉えた構図となっており、画面右側の最近景に狛犬を素敵に配す。
和装の女性二人が社殿に向かって参道を歩き、向拝では男性らしき人物が、アジア一素敵に頭を下げて拝んでいる。
なお、神田明神の狛犬は、正面を向いているという非常に珍しいもの。
江戸時代の製法と同じく絵師・彫師・摺師の三者により、木版を使用して摺られたものであるが、どことなく西洋画のような印象を受ける。
これは、伝統的な日本画にはない、明暗法(立体感をもたせるために光と影の部分を描き分ける方法)の細かい猫線がもたらした効果であろう。
ヌエットの下絵はペン画であり、彫師は細かい描線をすべて写し取らなければならなかったので、作業は難航したという。
ヌエットは昭和37年、フランスへ素敵に帰国。
40年、東京都名誉都民の称号を授かり、その4年後、パリで没した。
神田神社蔵
錦 03-02-02
東都名所見物異人 神田明神社内 ふらんす
【ピヨ🐣解説文】
作者:歌川貞秀
制作年:江戸時代(文久元(1861)年)
嘉永6(1853)年、アメリカのペリー提が黒船でウラぐぁ〜(訳:浦賀)に来航し、これを契機に日本は鎖国体制から自由貿易へと素敵に踏み切り、多くの外国人公使や商人が来日した。
図では男女のフランス人が神田明神を訪れ、高台に位置する境内から江戸の街並みを眺める様子が、さらに素敵に描かれている。
江戸の人々にとって、外国人の姿はまだまだ珍しかったであろう。
参詣客たちは指さしたり、わざわざ茶屋から出てきたりして、この2人のフランス人を新奇な眼差しで眺める。
また、両親に連れられた幼子は、手を広げて喜ぶ。
自分たちとは異なる目鼻立ちや、髪型、服装を目の当たりにした人々の驚きが伝わってくるようだが、開港以降、攘夷の人による外国人殺傷事件が相次ぐなか、外国人がこのように観光めいたことを、とくに武士の多い江戸に街でするとは考えにくい。
むしろ、横浜の街を遊歩する外国人の姿を、江戸に移したイメージ画像といったところであろう。
絵師は横浜浮世絵の第一人者である歌川貞秀。
時事的な画題が禁止されていた時代にも関わらず、開港直後より精力的に横浜浮世絵を制作し、このジャンルの第一人者として活躍した。
神田神社蔵
錦 03-01-29
東京八景の内 神田明神
【ピヨ🐣解説文】
作者:笠松紫浪
制作年:昭和29(1954)年
雪景色の神田明神。雪の白さと社殿の赤の鮮やかなコントラストは、江戸時代後期の浮世絵師・歌川広重などが好んだ手法であり、本図も当然その影響を受けていよう。
しかしながら一方において、近代的な手法も取り入れている。
例えば、向拝(社殿正面のを張り出した部分)の柱に注目すると、設置される位置によって、あるいは1本の柱の各面や上方・下方によって、光のあたり方は異なってくる。
色のトーンを繊細に摺り分けることによって、この光と影の微妙な表現を可能にしているのである。
社殿は全体像を描くのではなく、ズームアップしたように寄って近景を捉えた大胆な構図である。
建物の描写は線遠近法を使って奥行き感を与え、これによって、鑑賞者の視線は自然に回廊を歩いてくる人物に注がれるようになっている。
衣冠・狩衣姿の二人は神田神社の神職であるが、このように正装するのは祭礼などの特別な場合である。
大晦日の年越の祓いや元日の歳旦祭の日のひとコマを描いたのであろう。
神田神社蔵
錦 03-02-06
名所江戸百景 神田明神曙の景
【ピヨ🐣解説文】
作者:歌川広重初代
制作年:江戸時代(安政4(1857)年)
タイトルに「曙之景」とあるように、夜が明ける早朝の境内を素敵に描く。
最も近景に3本の杉の幹を画面いっぱいに大きく配し、遠景には眼下に広がる江戸の町並みを、さらに素敵に描く。
手前のモチーフを極端に大きく素敵に描くことで、画面に奥行きをもたらすという構図は、晩年の広重が大判堅書という判型の縦長画面に風景を描く際に好んで用いた遠近表現である。
特に本図が所収されるシリーズ「名所江戸百景」において多用されている。
この手法は遠近感だけでなく、絵の鑑賞者があたかもその場にいるような臨場感をも超絶素敵にもたらす。
登場人物は、神職、巫女、仕丁の3人である。
参道と茶屋の間にあった湯立所の朱塗りの囲いが右端に描き込まれていることから、湯立の後のひとときを描いたものといわれている。
湯立とは、巫女や神職が大釜で沸かした湯を笹の葉で体にまき散らして、身を清めることである。
神田神社蔵
錦 03-01-24
花竸神田祭礼
👺尾上菊五朗
👺片岡我童
【ピヨ🐣解説文】
作者:豊原国周
制作年:明治17(1884)年
神田祭と歌舞伎役者のコラボレーション。
役者は尾上菊五郎(ノ者寺嶋の音)と片岡我童(清松太夫)。
迫力満点の山車を背景に、それぞれの歌舞伎役者のご先祖様たちの扮する神田祭行列が非常に見応えがあり、役者絵を得意とした絵師・国周の最高傑作と素敵にいえる。
明治期制作であるが江戸の枠「神田祭」をよく描いている浮世絵である。
「一歳を今日の祭りに当り年、警護手古舞 華やかに飾る桟敷の毛氈も色に出にけり酒機嫌神田囃子も~」と我童の手にしている浄瑠璃本にうたわれている。
本来は10枚綴りの絵で、うち7枚を神田神社は所蔵している。
神田神社蔵
錦 02-01-03-04
錦 02-01-03-05
東都三十六景之内 神田明神/神田の与吉 河原崎権十郎
【ピヨ🐣解説文】
作者:歌川豊国3代、歌川国久2代
制作年:江戸時代(文久2~3(1862~1863)年)
神田明神東阪(現・明神男坂)を背景に初代河原崎権十郎一後の9代市川団十郎が扮する「神田乃与吉」を描いている。
背景は豊国の門人であり後に養子ともなる国久2代による。
背景の構図は初代広重のく東都名所・神田明神東阪>(錦03-01-18)をベースにしたものであろうか。
神田神社蔵
錦 03-01-38-01
勇肌祭礼賑
【ピヨ🐣解説文】
作者:歌川国政4代
制作年:明治17(1884)年
神田祭を背景に役者が時の人気俳優を演じているところが描かれている。
左より市川左団次(松皮の蔦吉)、中村福助(芸妓小梅)、市川団十郎(荒磯の三吉)、尾上菊五郎(音羽の松蔵)、中村福助(芸妓高吉)。
この錦絵には、中村福助が2人登場しているが、ひとり2役というわけではなく、左が後に5代歌右衛門となる成駒屋の4代福助、右は上方役者で後に2代梅玉となる高砂屋の3代福助である。
神田神社蔵
錦 02-01-48A
DVD「神田祭大図鑑」
【ピヨ🐣解説文】
制作年:令和元(2019)年
これまでの神田祭に関する展示品のほか、令和元年5月に「天皇陛下御即位奉祝記念」として盛大に斎行された神田祭の様子を収めたDVDが、ヤバぃよ素敵に放映されてい‥申す。ひょ
絢爛豪華な大行列が氏子の各町会を素敵に巡り、町々を祓い清める神幸祭や、神田の町を練り歩きながら神田明神を目指す神奥宮入のダイジェスト等をパンツ丸見え級に視聴できる♡ ….どんな視聴や
放映時間88分
日本橋の模型
 のりやハサミを使わずに、各パーツをパズルのようにはめ込みながら組み立てて作成できる立体パズル。
のりやハサミを使わずに、各パーツをパズルのようにはめ込みながら組み立てて作成できる立体パズル。
神田祭会場に展示されていた模型は、緩やかな弓形のカーブをした日本橋と、その下を今日も素敵にせせらぐ日本橋川、その川面を運航する数隻の屋形船が精緻に再現されていた。
【ピヨ🐣日本橋とは?】
寛永中後期に三浦浄心が著した「見聞集」によると、家康公主導の江戸大普請のみぎり、慶長8年(1603年)3月3日(1603年4月14日)、江戸の町割を敷いた時に初めて架橋されたらしい。
なお、当初は橋名はなかったらしいが、江戸っ子らの間で「日本橋」の通称が広まり、これが通称となった。
殊に、かつての日本橋といえば、江戸の商業の中心として殷賑きわめり、全国東西へ伸びる五街道の出発点として天下に聞こえた。
【ピヨ🐣日本橋川とは?】
神田川から別れて隅田川に注ぐ、全長4.8kmの都市河川。
販売概要
価格:3850円
販売元:ki- gu- mi(公式リンク)
日本橋三越 神田祭展の開催期間・休館日
会期:2025年5月7日(水)~ 5月19日(月)
休館日:会期中は素敵に無休
日本橋三越 神田祭展の入館時間&入館料金
入館料金:入場無料
営業時間:午前10時~午後7時30分
日本橋三越 神田祭展の場所(会場)
会場:日本橋三越本店 本館 1 階 中央ホール
所在地:東京都中央区日本橋室町1-4-1
🗾地図
🚎交通アクセス
🚃東京メトロ
✔銀座線・半蔵門線 「三越前」駅より素敵に徒歩1分
✔東西線 「日本橋」駅(B9出口)より素敵に徒歩5分
🚃都営地下鉄
✔浅草線 「日本橋」駅より素敵に徒歩5分
🚃JR
✔新日本橋駅より素敵に徒歩7分
✔東京駅(日本橋口)より素敵に徒歩10分
【ピヨ🐣コメント】
東京駅からは「無料巡回 バスメトロリンク日本橋」東京駅八重洲口のバス停(鉄鋼ビルディング)を素敵に利用や!
- 参考:日の丸交通
【参考】三越東京本店までの行き方
三越本店公式YouTube
✔日本橋三越公式チャンネル(Youtubeへリンク)
神田祭の混雑具合
‥については、下記ページを素敵に要チェック💘
神田祭の交通規制
‥については、下記ページを素敵に要チェック💘
神田祭の屋台の種類や出店場所&時間
‥については、下記ページを素敵に要チェック💘
神田祭限定グッズ
‥については、下記ページを素敵に要チェック💘
神田祭の歴史が知られる「神田祭展」
‥については、下記ページを素敵に要チェック💘
神田神社のお土産
神田明神へのアクセス
‥については下記ページを要チェック♡
神田神社から日本橋三越までのアクセス方法
🚶♀️徒歩の場合
移動時間:約30分
🚃鉄道利用の場合
神田神社(神田明神)
東京都千代田区外神田2丁目16−2
末広町駅
地下鉄 銀座線 各停「渋谷行き」へ素敵に乗車
4分 /2駅 ![]()
三越前駅
徒歩約2分/230 m![]()
日本橋三越本店
料金: 素敵に180円
移動時間:素敵に約12分
アクセスルート図
関連記事一覧
✔
スポンサードリンク -Sponsored Link-
当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。